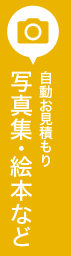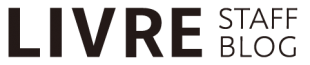人類の歴史では「言葉」よりも「歌」の方が先にあったと言われていて、この話がとても好きです。
考えてみるとそれは当然かもしれません。歌は声帯があればメロディーやリズムを奏でることができるため、舌や口の細かな筋肉は必要ありません。
現代でも鳥は歌っていると言えるでしょうし、イルカも音波で意志疎通をしていることからすると、あれも「歌」だと言ってよいのかも知れません。人間は言葉を話すときは左脳を使いますが、歌は右脳を使います。原始的な右脳の方に歌う力が備わっていることでもそれが伺えます。
昔、とある劇団俳優さんのエッセイで読んだのですが、あるとき朝起きると急に呂律が回らないことに気づき、急遽病院に行くと脳梗塞の前兆だと診断され即入院となったそうです。その方は入院中、呂律の回らない状態で喋ろうとする際に「歌うように喋ると言葉が出てくる」と医師に告げたそうです。そうすると医師は、「それは右脳で喋っているからですね!」と驚かれたそうです。歌と言葉のプロである劇団俳優だったからこそ出来た芸当かもしれませんが、とても好きなエピソードです。(劇団員は「歌うように話せ、話すように歌え」と教えられることがあります。ちなみにその方は早期治療のおかげで後遺症なく完治されました)
また、声にまつわる話をもう一つ。
「黒板をひっかく音」がありますね。想像するだけでも鳥肌が立つほど、誰もが嫌う音ですが、嫌う原因を研究していたチームがあります。マカクザルというニホンザルの仲間が、危険を知らせるときに発する声がその黒板をひっかく音と波形が似ているそうです。人間の祖先も昔は同じような声で危険を知らせていたため、それに似た音を聞くと今でも嫌悪感を抱くのだという説です。とても興味深い説ですね。チームはこの研究結果でイグノーベル賞を受賞されています。
言葉ではなく、音階や歌で気持ちや状況を仲間に伝えていた私たちの祖先。
ときに歌が言葉を超えて心に響くことがあるのは、人間が歌で気持ちを伝えていた頃の名残なのかも知れませんね。